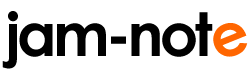ぷちミニマリストを目指して、55の捨てる方法を1つ1つ検証し、実践していくドキュメンタリー企画の第2回目です。
捨てる方法
捨てることは「技術」である
「捨てられない」という思い込みをまずは捨てて、捨てるという習慣を身につければ、「捨てる技術」もしだいに身につくそうです。
つまり、貧乏性の性格だからとあきらめかけていた人だって、考え方ひとつ変えてコツコツと捨てる行為を行っていけば、誰でもミニマリストになれるってことです。
捨てる作業よりも難しいこととは?
「捨てる」という具体的な作業は誰だってできます。
ゴミ箱のごみを捨てることから始め、本棚に飾りのようにずらずらーっと並べられているだけの本やCD、DVDなどをブックオフなどで買い取ってもらい、台所の棚奥にしまい込まれたジュースミキサーや、二度と電源の入ることのない健康器具をオークションに出品したり。。。
ある程度の時間や手間はかかるにしても、これらを処分することは可能ですよね。
でも、モノを処分するのに要する時間より、ずっとやっかいなのが、
モノに踏ん切りをつけて、処分することを決めること!
なんですよね。
- キツい練習に明け暮れた、大学時代の思い出のテニスラケット…
- 趣味でハマッたアコースティックギター…
- 誕生日に初めて彼女からもらった大切な腕時計…
そんな思い出の品は、そう簡単には捨てられそうにありません。
でも、この「捨てる技術」は、捨てるという行為によってはじめて身についてくるものだそうです。
そして捨てれば捨てるほど、この捨てる技術が上達し、やがては捨てる習慣が身につき、そして捨てるまでにかかる時間もしだいに短くなっていくようです。
今回のポイント
モノに向き合い、捨てる、捨てないと取捨選択をしていくうちに、自分のなかにも捨てる基準、残す基準が自然とできて、捨てるという経験の積み重ねが、捨てる技術を上達させてくれる。
実践したこと

思い出の品の1つ、パナソニックのLUMIX FZ2 をオークション出品しました。
当時では200万画素で、光学式手ブレ補正と光学12倍ズーム機能を備えたデジカメは珍しく、F値も全域2.8という明るいレンズは最強に思えました。
今でこそ200万画素は少なすぎって思えますが、一般的な写真プリントLサイズ(127mm×89mm)なら200万画素あればじゅうぶんなんですよね。
写真をA4サイズいっぱいに印刷することなんて、まずほとんどないし。

でもいつの間にか、デジカメは画素数を各社争うようになって、写真データを記憶するための保存媒体は大容量が求められ、お金はかかるいっぽう。
そんななか、このカメラは性能的にも必要じゅうぶんで、光学12倍ズームがあるから、旅行先でも大活躍した思い出のカメラでした。
ズーム機能を活かして、望遠側で人物撮影すれば、一眼レフのような自然なボケ具合を表現することもできましたし。

このカメラを買って、カメラのシャッタースピードであったり、絞りであったり、いろんな設定をすることで写真の表現を変えられることを教えてもらった気がします。
その後、一眼レフに憧れ続けるものの、値段が高過ぎてなかなか買うことができませんでしたが。。。
光学12倍ズームという機能を除けば、ほとんどの機能はいまのスマホでもじゅうぶん満たしてくれるので、これまでたくさんの思い出を写してくれたFZ2にはお礼をいってお別れしました。